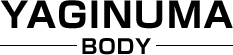近年の自動車は、パワートレイン、制動系、操舵系、快適装備まで、あらゆる機構が電子制御化されており、整備・点検における故障診断技術の重要性はかつてないほど高まっています。車両不具合の特定においては、従来の「感覚」や「経験則」に加え、電子制御システムの論理的把握と、専用診断機器によるデータ解析能力が必須のスキルとなっています。
現代の車両は、自己診断機能を備えたOBD-II(On Board Diagnostics)を標準装備しており、異常が検知されるとDTC(Diagnostic Trouble Code)を記録します。整備現場ではまず、スキャンツールをCAN通信経由でECUに接続し、登録されたDTCを読取・保存し、診断の起点とします。
ただし、DTCはあくまで「不具合の兆候」を示すものであり、直接的な故障原因を示すものではありません。例えば、「P0171:燃料系統が希薄」と表示されても、実際の原因がO2センサーの出力異常によるものか、あるいは吸気系のエアリーク、燃圧低下、インジェクター詰まり等の2次的要因によるものかは、ライブデータ解析やアクティブテストによる踏み込んだ診断が求められます。
整備士はここで、データストリーム(Live Data)を利用したリアルタイム診断を行います。例えば、クランキング時の回転信号の立ち上がり、スロットル開度と燃料噴射量の整合性、点火時期の補正量、燃料トリム(STFT/LTFT)といった数値の読み取りと、波形診断によるセンサー動作の整合チェックは不可欠です。
高度な診断にはオシロスコープやバッテリーアナライザー、ガスアナライザーなどの多角的な機器導入も必要であり、単なる「部品交換型」の整備から、「不具合解析型」の整備へと現場のスキル転換が求められています。
また、2024年からはOBD車検が義務化され、排出ガス関連の制御系(EGR、O2センサー、三元触媒等)の診断結果が、車検合否に直接影響することになります。つまり、単に「壊れている」ものを直すのではなく、車両が法的基準に適合しているかを定量的に判断できる能力が、これからの整備士に求められるのです。
加えて、ハイブリッド車やEVなどの高電圧系統の安全診断、およびそれらに対応する絶縁抵抗測定やバッテリーマネジメントシステム(BMS)診断といった知識・技能も不可欠です。今後の車両診断は「電気回路と論理思考の融合」がテーマになっていくでしょう。
総じて、故障診断とは「不具合の真因を科学的に解明する行為」であり、再発防止・予防整備・顧客信頼の維持に直結する最重要業務です。技術進化に即応した学習と実践を積み重ねることで、整備士はまさに「自動車の医師」としての役割を果たすことができるのです。